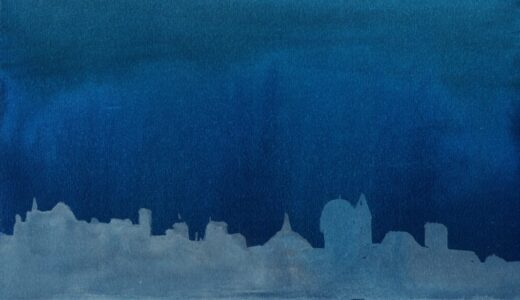各話のあらすじ(ネタバレ有)
1996年、横浜市の塾講師・戸川勝弘(宇野祥平)が、かつての教え子で軽度の精神障害を抱える阿久津弦(野田洋次郎)に殺害される。現場に残された指紋から阿久津が容疑者として特定されるも、彼は逃亡し、行方不明のまま2年が経過する。
1998年、旭西署の刑事課では連続強盗事件の捜査が進む中、窓際刑事の平良正太郎(吉岡秀隆)と新人刑事・大矢啓吾(高杉真宙)が、戸川事件の追跡捜査を命じられる。平良はかつて、上層部からの不正な指示に背を向けたことで旭西署への異動を余儀なくされた過去を、大矢に語る。それを聞いた大矢は、「必ず見返してやりましょう」と事件の真相解明に向けて闘志を燃やす。
平良と大矢は阿久津の過去を辿る中で、彼が戸川塾に通っていた頃の同級生や保護者に聞き込みを行う。戸川は障害を持つ子どもたちに対して献身的に接していた人物であり、悪評は一切見られない。平良は、阿久津が戸川に対して復讐心を抱いていた可能性を考えるが、証言からはその動機を裏付けるものは見つからない。
一方、小学生の橋本波留(小谷興会)は、親友の仲村桜介(小林優仁)との会話の最中に交通事故に遭い、左腕を骨折する。波留の父・太洋(吉岡睦雄)は事故の加害者である高齢女性に対し、息子の将来を盾に金銭を要求し、涙ながらに語る演技で大金を手にする。
スーパーで働く長尾豊子(瀧内公美)は、周囲に家族がいるように装っているが、実際には孤独な生活を送っている。夜、彼女は職場から売れ残りの総菜を持ち帰ると、2人分の食事を用意して地下室へ降りる。そこには逃亡中の阿久津弦が潜んでいた。
平良と大矢は、戸川殺害の背景を探るべく、阿久津が中学時代に起こした傷害事件に着目する。元担任の古屋は、阿久津が特に関係のない男子生徒に突然暴力を振るい、肋骨を折る重傷を負わせたことを証言するが、動機については不明だと語る。その事件以降、阿久津は周囲の生徒から恐れられ、次第に孤立を深めていったという。
一方、波留は父・太洋から林間学校への参加を許されず、誰にも助けを求められないまま、空腹をかかえて街をさまよう。偶然迷い込んだ長尾家の敷地で、地下室の窓越しに阿久津と出会う。阿久津は総菜を差し出し、波留は感謝の言葉を添えてその場で食事をとる。2人の間には奇妙な信頼が芽生える。
平良と大矢は、阿久津が事件直前に参加していた職場のバーベキューを調査する。参加者の森川は、阿久津が元妻との思い出を語っていたこと、そして子どもたちと楽しげに遊んでいた様子を語り、彼が子どもを強く望んでいた可能性が浮かび上がる。
元妻・実和(朝倉あき)は、阿久津との間に子どもができないことに責任を感じて離婚し、その後再婚して妊娠していた。この事実が阿久津にとって大きな衝撃となり、事件の動機に繋がったのではないかと平良は推察する。
平良自身の家庭では、息子・孝則(坂元愛登)がいじめを理由に登校を拒み、部屋に閉じこもる日々が続いていた。平良は何とか息子と向き合おうとするが、言葉は届かず、家族の間に深い溝が生まれていく。
阿久津を匿う豊子は、元夫・杉浦達男(柏原収史)と再会する。杉浦は財産分与を申し出るが、豊子はそれを断り、彼の再婚と子どもの誕生を祝福する。
夜、豊子は阿久津と夕食を共にしながら、中学時代の記憶を辿る。彼女は阿久津の傷害事件の現場を目撃しており、表面的にはいじめを止めるための暴力に見えたが、実際には「痛いか?」と問いかけていた男子生徒に“痛み”を教えるために殴ったのだと理解していた。豊子の目には、阿久津は何にも縛られず、自由に進む存在として映っており、その印象は今も彼女の中に強く残っている。
豊子が阿久津と再会したのは、両親の一周忌の帰り道だった。街灯の下に立ち尽くす阿久津に声をかけた豊子は、彼の「センセイを殺しちゃったから、警察署に行かなきゃ」という告白を受け止め、自宅に連れ帰ったのだった。今、地下室で共に過ごす時間の中で、豊子は阿久津に「ありがとう。うちに来てくれて」と静かに語りかける。
平良と大矢は、阿久津の元妻・真木実和(朝倉あき)から話を聞き、阿久津が父親から虐げられ、結婚や家庭を持つことを否定され続けてきたことを知る。そんな阿久津が結婚に踏み切ったのは、戸川の存在があったからだった。
阿久津にとって戸川は、向かうべき方向を照らす人生の道しるべのような存在だった。しかし、なぜその戸川を殺害するに至ったのか、その動機は依然として掴めない。平良たちは、事件当日の阿久津の行動を知るため、聴取を拒んでいる母・栄子(キムラ緑子)のもとを訪ねる決意を固める。
一方その頃、阿久津を匿う豊子の家では、少年・波留が阿久津に心を開き始め、彼のもとを頻繁に訪れるようになっていた。阿久津の人柄に触れた波留は、やがて地下室にまで足を踏み入れるが、その姿を友達の桜介に目撃されてしまう。
桜介は、以前テレビで見た「逃亡中の殺人犯・阿久津弦」の顔を思い出し、地下室に潜む男がその本人であると確信する。
豊子は阿久津が誰かに見つかることを恐れ、彼を匿い続ける日々に神経をすり減らしていく。その一方で、阿久津との関係を深め、彼が罪を犯していなければ普通の恋人同士として生きられたのに、と儚い願望を吐露する。
平良と大矢は栄子の家を訪ね、事件当日に阿久津が「実和が妊娠して再婚する」と語ったことを聞き出すが、栄子の証言には不自然な点が多く、彼女が何かを隠していることが明らかになる。
さらに「みんなやってるって言うから」という謎の言葉や、「平山」という人物の名前を口にし、事件の背後に新たな影が見え隠れする。大矢は焦りから栄子を追及しすぎて失敗し、二人は手がかりを失いかけるが、平良は粘り強く調べる決意を固める。
そんな矢先、平良の妻・澄子(映美くらら)から「孝則が!」という切迫した電話が入り、電話の向こうで救急車のサイレンが鳴り響く。
病院に駆けつけた平良は、妻・澄子から孝則が自宅の窓から飛び降りたことを知らされる。命が助かったことに安堵するも、家庭内での自らの言動が息子を追い詰めた可能性に気づき、深い苦悩に陥る。澄子との対話を通じて、親としての在り方を見つめ直した平良は、息子にとって安心できる居場所をつくることの重要性を痛感し、仕事よりも家族を優先する決断を下す。
その頃、平良の同僚・大矢は、戸川塾の元生徒・平山幸子(坂東希)と接触。殺害された塾講師・戸川が生徒ごとに「指導ノート」を記していたことを知る。阿久津の母・栄子が口にした「みんなやってる」という言葉の意味を探るため、平良と大矢は戸川塾に保管されていたノートを調査し、幸子の母・弘子が〈親の会〉に参加していた事実を突き止める。
2人は〈親の会〉事務局を訪ね、1975年の座談会の録音テープと写真を入手する。テープには、知的障害児を持つ親たちが「優生手術」について語る衝撃的な内容が記録されており、医師が子どもを妊娠させないための断種を推奨していた。幸子が「妊娠しない」と語っていたことや、阿久津も同様の手術を受けていた可能性を踏まえ、「みんなやってる」とは優生手術のことだったのではないか、と2人は推測する。
一方、波留は阿久津と親しくなり、彼の過去や元妻・実和との思い出を聞く。波留が林間学校について語ると、阿久津はかつて実和と日光を訪れた際の記憶を語り、「一緒に日光へ行こう」と波留に告げる。だが、波留の前に現れた桜介が阿久津の指名手配写真を見せ、警察へ行こうと誘う。波留はそれを拒み、「絶対に通報するな」と忠告してその場を立ち去る。
波留の父・太洋は、息子が他人から食べ物をもらっていたことに激怒し、豊子の家に乗り込む。豊子はとっさに「私が食べ物をあげました」と嘘をつき、波留と阿久津を守る。豊子自身も過去に流産や離婚、両親の事故死を経験し、孤独と喪失の中で生きていた。阿久津との関係が揺れ動く中、彼から「日光に行こうと思ってる。車を貸してほしい」と頼まれるが、豊子はそれを拒否する。
平良と大矢は20年前の優生手術の実態を探るため、泌尿器科の病院を訪れ、理事長に直接問いかける。
阿久津は豊子に波留が抱える事情を話す。豊子は阿久津の気持ちを尊重し、彼を解放する。阿久津は「日光へ行く」という波留との約束を果たすため、豊子の車を借り、波留の家へ向かう。
波留は阿久津の訪問に驚きながらも、共に出発する決意を固める。父・太洋は波留を車から引きずり出そうとするが、阿久津は「生まれてこなきゃよかった子どもなんていない」と言い放ち、太洋を車で撥ねて波留とともにその場を離れる。
一方、平良と大矢は阿久津の母・栄子を再び訪ね、過去の優生手術の真相に迫る。阿久津が15歳のとき、栄子は彼を病院に連れて行き、不妊手術を受けさせていた。きっかけは、阿久津がリビングで性的な雑誌を見ていたことだった。
栄子は平山や戸川の助言を受け、「子どもを生まない方が阿久津のためになる」と信じて手術を決断したという。事件当日、栄子はその事実を阿久津に告げたが、「私が言わなければ、あんなことは起こらなかった」と号泣する。
阿久津と波留は日光へ向かう道中、互いの家族について語り合う。波留は父との思い出がほとんどなく、肩車すらしてもらったことがないと語る。平良と大矢は太洋の証言から阿久津の関与を確信し、2人の行き先が日光であると推測して追跡を開始する。
中禅寺湖の駐車場に到着した阿久津と波留は、林間学校のバスを目にする。そこへ警察車両が到着し、井筒が拡声器で阿久津に呼びかける。波留の友人・桜介がバスの中から波留の名前を呼んだことから、阿久津は車を降り、平良に「波留を林間学校に参加させてほしい」と頼む。
平良は教師の岡野に確認を取り、参加が可能であることを伝える。阿久津は波留を肩車し、「いろんなものを見て、しまっておけよ」と告げる。波留は保護され、阿久津は警官に取り押さえられる。
平良は息子・孝則の手術前に病室で語り合う。自分の価値観を押しつけていたことを謝罪し、「弱くたってかまわない。孝則の人生は、孝則のものだ」と伝える。そして「生まれてきてくれて、ありがとう」と言葉をかける。
豊子は警察に出頭し、阿久津を匿っていたことを告白する。そして自分のような無関心な人間が彼を傷つけ、踏みにじり、追いやったのだと語る。
阿久津の取り調べは難航していたが、平良は井筒の許可を得て彼と面会する。戸川はどんな存在だったのかという平良の問いに、阿久津は補導された夜に戸川が警察まで迎えに来てくれたことを語る。「暗い中で、先生の白い服の腕だけが見えた。あの手のさすほうへ行けば、間違いないんだって思った」と。
感想(ネタバレ有)
事件と社会構造に重点を置いたドラマ版
見終わったあとも映像の美しさと音楽の余韻が心に残る作品でした。特に最終話は、印象的なシーンが続き、胸に刺さる言葉も多かったです。
物語の流れは原作にしっかりと沿っていて、違和感なく楽しめました。ドラマならではの追加シーンやオリジナルのエピソードも自然に組み込まれていて、見ごたえのある仕上がりだったと思います。事件の真相に迫る展開は緊張感があり、毎回「次が気になる」と思わせる力がありました。
ただ、原作では登場人物たちの複雑な内面や葛藤が丁寧に描かれていて、そこに強く惹かれていたのですが、ドラマではそのあたりがだいぶシンプルにまとめられていました。
ドラマが「社会派ミステリー」としての構成を優先して、社会の構造や事件のつながりに重点を置いていたことは理解できますし、こうした繊細で重層的なテーマを映像で表現するのはとても難しいことだとも思います。そうした演出の意図もふまえながら、作品を振り返ってみたいと思います。
刑事の視点で進むわかりやすい展開
ドラマ版は、刑事・平良の視点を中心に物語が進んでいきます。原作では、登場人物の視点が次々と切り替わる群像劇になっていましたが、ドラマでは「阿久津の殺人の動機を追う」という明確な目的のもと、捜査の流れに沿って話が進むため、とてもわかりやすかったです。
ベテラン刑事の平良と、新人の大矢のコンビも魅力的でした。経験豊富で落ち着いた平良と、まっすぐで少し不器用な大矢の組み合わせが、緊張感のある捜査の中にも人間味を感じさせてくれて、見ていて飽きませんでした。
また、登場人物たちが最初はまったく関係がないように見えて、少しずつ阿久津と繋がっていく構成も面白かったです。誰がどこでどう関わってくるのかが徐々に明らかになっていく過程は、原作の面白さをしっかり引き継いでいました。
終盤では、阿久津の母・栄子が口にした「みんなやってる」という言葉をきっかけに、平良と大矢が事件の核心である「優生保護法」にたどり着くまでの流れが丁寧に描かれていて、目が離せませんでした。少しずつ真実に近づいていくその過程が、ドラマ全体の緊張感を高めていたと思います。
平良が映し出す男性の生きづらさ
原作にはない平良の家族のエピソードも興味深かったです。仕事では阿久津の気持ちに寄り添える平良が、家庭では息子・孝則の本音にまったく気づかず、向き合おうとしない姿が描かれます。
孝則の不登校と引きこもりは、最初はいじめが原因だと思われていましたが、物語が進むにつれて、父親である平良の考え方や態度が、実は彼を追い詰めていたことがわかってきます。
平良は家庭の中で起きていることには無関心で、息子と話すのも「妻にうながされて」しぶしぶといった態度。孝則の話を聞くふりをしながら、弱さを「恥ずかしいこと」として否定し、最初から自分の価値観を押しつけていました。
この姿は、昔ながらの「父親像」を思わせます。わたし自身も、そういう父親を見て育ったので(うちの父は明治時代のような人でした)、当時はそれが“普通”だと思っていました。
この物語には、阿久津の父、波留の父、塾講師の戸川など、いろいろな父親が登場します。波留の父は元バスケット選手で、引退後に社会にうまくなじめず、人生が崩れていった人です。戸川は塾の仕事に夢中になりすぎて、家庭をおろそかにしてしまい、離婚しています。
波留の父と戸川の過去はドラマでは描かれませんでしたが(設定も少し違うようでした)、平良の家庭の描写が加わったことで、「父親としての葛藤」や「男性が抱える生きづらさ」が現代的な視点で浮かび上がっていたと思います。
主人公の平良が、何度も失敗しながらも息子との関係を取り戻そうとする姿には、多くの人が心を動かされたのではないでしょうか。
母親たちの叫びと、描かれなかった“違和感”
この物語に登場する“母親”たちについても、触れておきたいと思います。
最終話、キムラ緑子さん演じる阿久津の母・栄子が、平良たちに「秘密」を告白するシーン。それまで彼女がひとりで抱えてきた苦しみや罪の意識が一気にあふれ出し、怒りと共にぶつけられます。
優生保護法は、1948年から1996年まで続いていた「法律」です。栄子の「だって、国がそうすべきだって言ったんじゃないですか!」という叫びが、今も耳から離れません。
「私は、間違ったことをしたんですか? 正しいことだと信じたのに、後になってあれは間違いだった、そんな人権侵害はありえないって言われたって、今更どうすればいいんですか?」
時代によって「正しさ」が変わる残酷さ。気がついたら世の中の価値観が変わっていた、という経験をしたことがある人は、少なくないはず。でもそれが、命にかかわることで、取り返しのつかないことだったら……?
一方で、阿久津の元妻・実和や、同級生の豊子は、ドラマでは「子どもを望んでいたけれど、それが叶わず傷ついた女性」として描かれていました。
原作では、「母になること」への違和感や、自分の身体と心がうまく噛み合わない感覚、そして社会から押しつけられる“母性”の重さといった部分まで踏み込んでいて、彼女たちの痛みがより深く掘り下げられていました。
ドラマは全5話という短い構成だったので、登場人物それぞれの心の動きや背景をすべて丁寧に描くのは、きっと難しかったと思います。それでも、彼女たちが感じていた違和感や女性として生きることのしんどさ、周囲からの無言のプレッシャーは、社会のしくみを考えるうえでとても大切な視点だったと思います。
わたし自身、原作で描かれていた豊子の内面描写には、救われる部分がありました。だからこそ、ドラマでその描写が省かれていたことに、少し寂しさを覚えました。
見向きもせずに、通り過ぎてきた
最終話で、出頭した豊子が大矢に語った言葉が心に残りました。
「それは、今まで私が見向きもせずに、通り過ぎてきたことでした。そんな自分こそが、彼を傷つけ、踏みにじり、追いやってきたんだって知ったんです」
1996年当時、わたしはすでに社会人でしたが、「優生保護法」について聞いたり話したりした記憶がありません。豊子の言葉のとおり、わたしも「見向きもせずに、通り過ぎてきた」ひとりだったのだと思います。
知らなかったことが、誰かを傷つけていたかもしれない。社会の中で、自分でも気づかないうちに「加害者」になってしまうことがある。その事実に向き合うのは怖いことですが、だからこそ責任を持って考え続けなければならないと感じました。
原作では、登場人物たちが抱えていた「誰にも理解されない痛み」や、「こうあるべきという社会の圧力への違和感」が、もっと丁寧に描かれています。
もし機会があれば、ぜひ原作も読んでみてください。ドラマと原作の両方を味わうことで、この作品が投げかけている問いの深さに、より気づけるのではないかと思います。
そのほかの記事