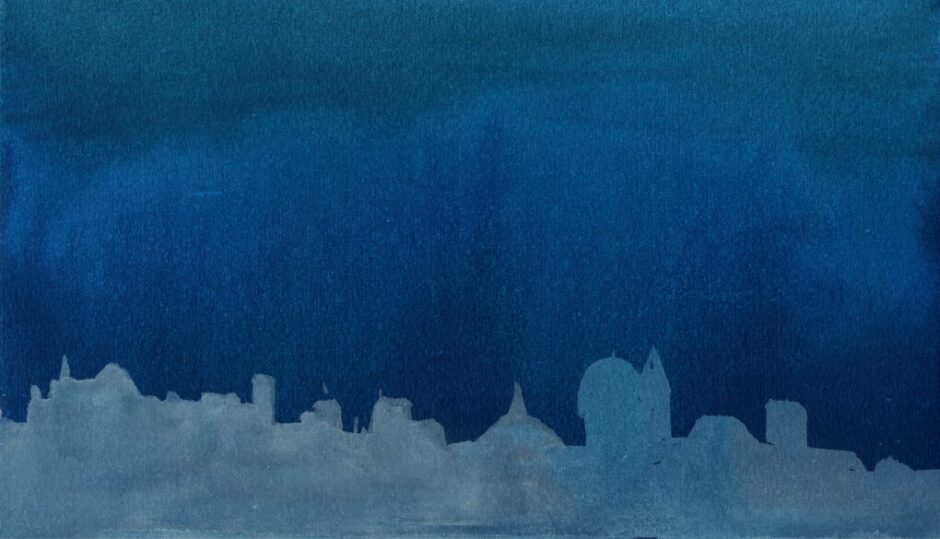芦沢央さんの長編小説『夜の道標』を読みました。塾経営者が元教え子に殺された事件を軸に、社会の暗部を描いた本格的な社会派ミステリーです。
物語が進むにつれ、1990年代という時代設定が物語の核心に深く関わっていることに気づきます。それは過去のできごとにとどまらず、現代を生きるわたしたちの心にも問いかけてくるものでした。
『夜の道標』は、声をあげることができなかった人たちの思いに寄り添う物語です。登場人物たちは、それぞれの立場で“言いたくても言えない気持ち”を抱えていますが、それは語ることが難しかった時代の空気の中で育まれたものでした。
そんな彼らの心の声に耳を傾けながら、作品を読み解いていきたいと思います。
※本記事は作品をすでに読まれた方を対象としています。物語の重要な部分に触れていますので、未読の方はご注意ください。
▼ドラマの記事はこちら
 ネタバレ有「夜の道標-ある容疑者を巡る記録-」全話あらすじ・感想・登場人物(キャスト)一覧|あの時代に見えなかった罪
ネタバレ有「夜の道標-ある容疑者を巡る記録-」全話あらすじ・感想・登場人物(キャスト)一覧|あの時代に見えなかった罪 歪んだ道標の先に生まれた悲劇
物語は、登場人物それぞれの視点から語られます。
平良正太郎は、上司から疎まれ、窓際に追いやられたベテラン刑事。彼は新人刑事の大矢とともに、1996年に発生した塾経営者殺人事件(作中では2年前の出来事)を粘り強く追い続けています。
被害者は塾講師の戸川勝弘。生徒や保護者から厚い信頼をよせられていた人物で、誰かに恨まれるような存在ではありませんでした。そんな戸川が、彼を慕っていた元教え子・阿久津弦によって命を奪われた理由とは何だったのか。
平良と大矢は、逃亡中の阿久津を見つけ出す手がかりとして、戸川殺害の動機を探ろうとします。
捜査が進むにつれ、戸川の知られざる一面が明らかになります。彼は精神障害を抱える阿久津に対し、優生保護法に基づく不妊手術を母親に勧めていたのです。
優生保護法とは
1948年から1996年まで日本で施行されていた法律です。「不良な子孫の出生を防ぐ」と「母体の健康を守る」ことを目的としていました。
この法律により、障害や特定の病気を持つ人に対して、本人の同意なしに不妊手術が行われることがありました。背景には「優生学」という、遺伝的に“望ましくない”とされた人々の生殖を制限しようとする考え方があり、人権侵害として後に強く批判されました。
優生保護法は1996年に法改正され、差別的な条文は削除されて「母体保護法」となりました。現在では、被害者への補償や謝罪が進められています。
阿久津にとって戸川は、暗闇の中で進むべき方向を示してくれる「道標」のような存在でした。誰かが指し示す方向があるだけで、人は安心できる。けれど、その道標が誤っていたとしたら――。
この作品では、「道標」という言葉が繰り返し登場します。それは、他者の言葉や価値観に従うことで、自らの選択をゆだねてしまうこと。そして、その道標が制度や社会の通念によって歪められていたとき、どんな悲劇が生まれるのかを問いかけているのです。
登場人物の関係性から読み解く構造
「言葉にできない心の傷」や「誤った道標」が、どのように人から人へと受け継がれ、連鎖していったのか。物語に登場する人々の関係性をたどっていくと、物語の深い構造が見えてきます。
戸川と阿久津:信頼と制度のすれ違い
阿久津弦は、社会のルールや規範から逸脱した存在です。そんな彼にとって、塾講師の戸川は人生の「道標」でした。戸川の言葉に従えば間違いない、彼はそう信じていたのです。
けれど、道標そのものは「善」ではありません。、道標が立っている場所が腐食していれば、まっすぐな矢印ほど、まっすぐ間違ってしまう。
戸川は阿久津に「生まれてこなきゃよかった子どもなんていない」と言いながら、阿久津のもとに生まれてくる子どもを否定しました。それは阿久津の存在そのものを否定していることにもなります。
戸川自身は善意で動いていたのかもしれません。教育に熱心で、生徒の進路にも親身になっていた人格者です。でも、その「正しさ」が、誰かの人生を傷つけてしまうこともあるのです。
2人の関係は「信じていた人に裏切られた」という単純な話ではなく、「信じることしかできなかった状況」が、どれほど危ういかを教えてくれます。制度の中で生きる人間同士の、複雑なすれ違いがここにあります。
阿久津と豊子:理解できない他者との距離
阿久津を匿っていた同級生の長尾豊子もまた、社会になじめず、生きづらさを抱えていました。彼女は、あたりまえのように求められる「他者との関係」をうまく築けず、必死にもがいている存在です。
中学時代、豊子は阿久津が起こした暴行事件を目撃しました。周囲の人は、阿久津がいじめられている子を助けた、と思い込んで美談に仕立て上げましたが、実際は違います。彼はいじめっ子が「痛いか?」と聞きながら殴っていたから、痛いかどうか教えてあげようと“親切”で殴ったのです。
豊子だけがその歪んだ論理をまのあたりにし、衝撃を受けます。他人と自然に関われないことに悩みながらも、それをうまく言葉にできず、孤独の中で自分を責め続けていた豊子。彼女の目には、社会から理解されずとも、自分を無理に変えようとせず飄々と生きている阿久津の姿が、まぶしく見えたのかもしれません。
結婚、流産、離婚、両親の死といった人生の節目で、豊子は何度も「関係の終わり」を経験します。阿久津との再会は、そんな彼女が「誰かと向き合う勇気」を、もう一度手にしようとする瞬間でもありました。
しかし、逃亡中の阿久津との関係を続けるということは、彼を守ると同時に「閉じ込める」ことにもなります。それははたして「愛情」と呼べるのか。「支配」ではないのか。迷い悩んだ末に、豊子は阿久津の選択にゆだねます。
豊子は「理解できない他者」を無理に理解しようとせず、ただそばにいることを選んだ。それは、正しさを押しつけるよりも、ずっと誠実な態度だったと思います。
波留と太洋:父性の呪縛と暴力の連鎖
小学生の波留にとって、父・太洋はまさに「道標」でした。
バスケットボールを教えてくれた父は、最初は頼もしく、憧れの存在だったかもしれません。けれどその「導き」は、次第に大きく歪んでいきます。
太洋は、「男らしさ」や「父親らしさ」といった社会的な規範に縛られ、自分の弱さや不安を誰にも打ち明けることができませんでした。定職に就かず、生活が不安定な中で、彼は「父としての威厳」を保つために、暴力や支配という手段に頼ってしまいます。これは、現代にも通じる「男性が弱さを見せられない社会」の縮図でもあります。
そのストレスの矛先は、最も身近な存在である息子・波留に向けられます。波留は、父の思いつきで「当たり屋」を強要され、「才能ある子どもが不幸に見舞われた」という物語を演じさせられます。慰謝料を得るための道具として扱われた波留は、父が大金を手にすると、あっさりと置き去りにされてしまいます。
残された波留は、わずかな金で生活をしなければならず、常に空腹と孤独に苦しみます。それでも、父に逆らうことができません。誰かに話せば、父も自分も傷つく。だから黙っているしかない。
しかし、波留は友人の桜介にだけ、思わず本当のことを話してしまいます。語ることで、波留の中に風穴が開き、少しずつ変化が始まります。言葉にすることで、自分の苦しみを客観視できるようになり、他者との関係性にも新たな可能性が生まれていくのです。
太洋の導きは、本来なら息子を守るための「道標」であるべきでした。けれどその道標は、いつの間にか支配の道具となり、波留の人生に深い影を落とします。これは、親が子に与える「価値観」や「生き方のモデル」が、時に暴力的に作用することへの警鐘でもあります。
社会が「こうあるべき」と押しつける父性や家族像が、個人の尊厳を奪ってしまうことがある。波留と太洋の関係は、その危うさを浮き彫りにしながら、「本当に子どもを導くとはどういうことか」を問いかけてきます。
阿久津と波留:語れない傷がつなぐ絆
殺人犯の阿久津と、小学生の波留。一見するとまったく接点のない2人ですが、それぞれが「語ることができない心の痛み」を抱えているからこそ、惹かれ合っていったのだと思います。
阿久津は地下室に潜んで生きていて、社会から切り離された存在。過去の罪に向き合いきれず、孤独の中にいます。一方、波留は父親からネグレクトを受け、「当たり屋」を強要されるという、誰にも言えない苦しみを抱えています。
そんな2人が偶然出会い、少しずつ距離を縮めていく過程は、深い余韻を残します。阿久津は波留に対して、何かを教えようとしたり、導こうとしたりはしません。ただ、そばにいてくれる。波留にとって阿久津は、初めて「何も奪わない大人」だったのかもしれません。
波留は、友達の桜介から「あいつは殺人犯だ」と告げられても、阿久津を拒絶しません。阿久津の過去よりも、今の彼を見ているからです。誰かの痛みを理解できるのは、自らも痛みを抱えている人だけ。
言葉にできない傷を抱えた者同士が、そばにいることで支え合う。物語の中でひときわ優しく、力強く描かれている2人の絆が、この物語のもうひとつの「道標」なのだと思います。
時代設定の意味と現代への問い
物語の舞台は1990年代。読み始めたときは、なぜこの時代なのか少し不思議に感じました。でも物語が進むにつれて、1990年代という時代が持つ“空気”が、登場人物たちの“沈黙”に深く関わっていることがわかってきます。
この頃は、まだインターネットも携帯電話も一般には広まっていませんでした。情報は限られた場所からしか得られず、医師や教師、親といった身近な“権威”の言葉が、何よりも強く響いていた時代です。自分で調べることも、同じ境遇の人の声を聞くことも、今ほど簡単ではありませんでした。
だからこそ、戸川のような人物が「正しいこと」として語る言葉が、阿久津やその母にとっては絶対的な道標になってしまったのだと思います。優生保護法のような制度も、「みんなやっている」「子どものため」という言葉と一緒に、日常の中に溶け込んでいたのでしょう。
この作品は、そうした“語られなかった制度”が、社会の中にどんなふうに沈殿していたかを描いています。そして、それがどれほど個人の選択や人生に影響を与えていたかを、鋭く問いかけてきます。
一方で、今の時代はというと…。SNSや検索エンジンを使えば、誰かの体験や声にすぐに触れることができます。多様性や人権についての議論も、以前よりは開かれたものになってきました。昔に比べれば、話せるようになったことは確かに増えました。
でも、まだ話せないこともあります。声を上げるのが怖い人もいるし、自分の痛みを言葉にできない人もいる。それは、時代が変わっても、社会の中に残り続ける“沈黙の壁”なのかもしれません。
読後の余韻と希望の灯り
この作品を読み終えたあと、わたしの中にいくつかの問いが残りました。
自分が信じる“正しさ”は、30年後も正しいと言えるだろうか。
言葉にできない誰かの痛みに、耳を傾けてきただろうか。
語ることができなかった自分自身の声に、今なら向き合えるだろうか。
こうした問いは、すぐには答えが出ません。でも、問いを持ち続けることそのものが、語れなかった過去に光を当てる行為なのだと思います。
この物語には、はっきりとした「救い」はありません。阿久津はどうなったのか、太洋は罪を問われるのか、豊子は罰せられるのか――その答えは、作中では語られていません。
けれども不思議なことに、読後には何かあたたかいものが残ります。誰かが誰かの痛みに寄り添った時間があったこと。それが希望のかたちとして心に残っているのです。
豊子が阿久津の思いを受け止め、彼を匿ったこと。阿久津や桜介が、波留の言葉に耳を傾けたこと。それらは、誰かを完全に救うことはできなくても、「あなたの痛みはここに置いていい」と伝える行為だったように思います。
そしてそれは、読者であるわたしたちにも向けられたメッセージのように感じられます。
語れなかったことを語ること。語れない誰かの声に耳を傾けること。その小さな積み重ねが、社会の中に少しずつ希望を灯していくのだと思います。
そのほかの記事