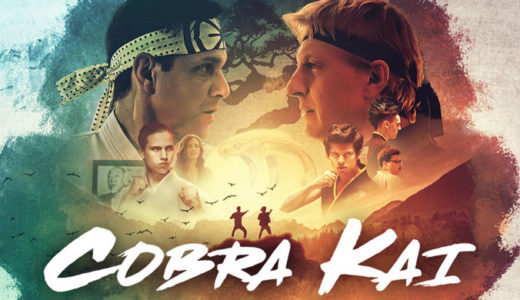Contents
感想と解説(ネタバレ有)
コロナ禍とセレブ文化の皮肉
今回の舞台は、まさにコロナ禍の真っ只中。登場人物たちはマスクをしていたり、ワクチンらしきスプレーを噴射されたりと、現実のパンデミックが物語にしっかり組み込まれています。これが、前作よりも現実味を強く感じる理由のひとつ。
そんな状況下でも、セレブたちは自分の世界にどっぷり。パーティーを開いたり、SNSで炎上したり、政治や科学を“ビジネス”として扱ったり。彼らの振る舞いは、まるで現実を無視しているかのようで、セレブ文化への痛烈な風刺になっています。
たとえばバーディーは、ロックダウン中に「スウィーティー・パンツ」という高級ジャージを売り出して大儲け。でもその製造元は劣悪な環境のブラック工場で、彼女はその責任をまったく理解していない。
政治家のクレアは選挙支援の見返りとしてマイルズの発電所を認可し、科学者のライオネルは“クリア”の危険性を知りながら有人ロケットに使う許可を出してしまう。
こうした描写は、現代社会の“見せかけの正義”や“権力への従属”を浮き彫りにしていて、観ていてちょっとゾッとする部分でもあります。
そして、名探偵ブランもまた、ロックダウンで暇を持て余す人物として登場。彼が風呂場に入り浸ってオンラインゲームにふけるシーンは、孤独と退屈を象徴するユーモラスな演出でありながら、現実の閉塞感をさりげなく映し出していました。
グラス・オニオンの構造
「グラス・オニオン(ガラスの玉ねぎ)」というタイトルは、物語の構造そのものを表しています。
舞台となるギリシャの孤島に作られたマイルズの邸宅は、ガラス張りの未来的な建築物で、中心には玉ねぎ型のドームがそびえ立っています。
見た目はすべてがオープンで透明。でも、実際にはその“透けて見える構造”が、逆に真実を隠しているという皮肉な仕掛けになっているんですね。
この空間は、マイルズが築いた“虚構の世界”そのもの。彼は「透明性」を演出しながら、実際には嘘と演出で周囲を支配しています。まさに、見えているようで見えていないという構造が、物語のテーマとぴったり重なる。
衣装もまた、この空間と呼応しています。セレブたちはそれぞれ、自分をどう見せたいかを服装で演出しています。派手な色、奇抜なデザイン、ブランド志向──どれも「私はこういう人間です」と主張するための“仮面”のようなもの。
一方で、ヘレンの衣装はシンプルで実用的。アンディになりすますための変装も、虚構の世界に入り込むための“鍵”として機能しています。そしてラストで感情が爆発する場面では、衣装も乱れ、彼女の“素の姿”があらわになります。
つまり、空間と衣装の両方が、「虚構と真実の境界線」を視覚的に語っている。「グラス・オニオン」というタイトルは、物語の構造・テーマ・演出すべてを貫くメタファーになっているのです。
名画の炎上が意味するもの
ヘレンがマイルズの世界を燃やし尽くすラストシーンは、爽快でありながら、単純にスカッとできない葛藤がありました。
まず、ヘレンが選んだのは「法では裁けない悪」に対して、行動で真実を示すという手段。マイルズは罪の証拠(会社のアイデアを書いた紙ナプキン)を燃やし、仲間たちも沈黙を選び、司法では裁けないことが明らかになる。
そんな状況でヘレンが選択したのは、“透明なウソを破壊することで真実をさらす”ことでした。
彼女が取った行動の中でも特に衝撃的だったのが、名画「モナリザ」の炎上です。人類の文化遺産とも言える名画を燃やすという行為は、倫理的には完全にアウト。でも、それをあえてやったことで、マイルズの虚構が世界にさらされることになった。つまり、芸術を犠牲にして得た“真実”と言えます。
この選択には、「正義のために何を犠牲にできるか?」という難問が含まれています。ヘレンはアンディの無念を晴らすために、マイルズの「永遠に語り継がれたい」という欲望を逆手に取り、最悪の形で歴史に残るよう仕向けたわけです。
そしてもうひとつ大事なのは、ヘレンがこの破壊を誰かに命じられたわけではなく、自分の意思で選んだということ。ブランは「勇気を与えることしかできない」と言って、“クリア”の破片を渡すだけ。最終的な判断は、ヘレン自身が下したのです。
このラストは、「正義とは何か?」「倫理とは誰が決めるのか?」という問いを観客に突きつけてきます。ヘレンは破壊によって真実を可視化し、マイルズの虚構を終わらせた。彼女こそが、本物の“破壊者”だったんですね。
わたしなら…「モナリザ」を燃やすことはできないかも。あの一瞬で即決してダッシュする機敏さは、わたしにはないです。
アンディとヘレンの共通点
アンディとヘレンは、見た目はそっくりでも性格も生き方もまったく違うように見えます(ジャネール・モネイの演じ分けがお見事)。
アンディはテクノロジー企業の創業者で、知的で冷静。ヘレンはアラバマの小学校教師で、感情豊かで素朴な印象。でも物語が進むにつれて、2人の深い共通点がじわじわと浮かび上がってくる。
まず、どちらも正義への強い信念を持っています。アンディはマイルズの不正に対して法的に闘い、ヘレンはその不正を暴くために命がけで行動します。手段は違っても、「真実を守る」という目的は同じ。
そして、2人とも知的な洞察力を持っています。アンディはアルファ社のアイデアを生み出した天才的な起業家。ヘレンも、姉の死の真相を探る過程で冷静に状況を分析し、証拠を見つけ出します。タイプは違っても、どちらも“頭の切れる人”です。
さらに、行動力と勇気も共通しています。アンディは孤立を覚悟でマイルズに立ち向かい、ヘレンは危険を冒して島に潜入。どちらも「自分の信じるもののために動ける人」なんですよね。
ラストでヘレンが「モナリザ」を燃やすシーンは、アンディの無念を晴らすだけでなく、2人の怒りと悲しみが重なった瞬間でもあります。あの破壊は、姉妹の“共通の魂”が爆発したようにも見えました。
アンディが「創造者」なら、ヘレンは「破壊者」。でもその根っこには、真実を守りたいという同じ想いがある。2人は対になる存在ではなく、補完し合う存在なんですね。
ブノワ・ブランとデロルの正体
名探偵ブノワ・ブランは、今回も“事件を解決する人”というより、真実へと導く案内人として描かれていました。彼の役割は、単に犯人を暴くことではなく、ヘレンが正義を実行するための土台を築くことだったんです。
ブランの立ち位置と役割
- マイルズとは真逆の存在
マイルズのような“空っぽの天才”とは対照的に、ブランは知性と誠実さを兼ね備えた人物として描かれています。彼の推理は、論理だけでなく人間性にも根ざしているのが魅力です。 - 行動を他者に委ねる探偵像
ラストでブランは、「モナリザ」を燃やすかどうかの選択をヘレンに委ねます。これは、探偵が“真実を暴く”だけでなく、“正義の実行”を他者に託すという、新しい探偵像の提示でもあります。
デロルの正体と意味
- 物語に関与しない男
マイルズの島に住み着いている“謎の男”デロルは、何度か登場するものの、事件にはまったく関与しません。彼の存在は、観客に「何かあるのでは?」と思わせるミスリードの装置でもあります。 - 監督の遊び心
デロルを演じているノア・セガンは、ライアン・ジョンソン監督の作品に常連として登場する俳優。つまり、デロルは“監督の遊び心”として登場しているキャラクターです。 - “何もない”の象徴
何かありそうで何もない。これは、マイルズの虚構の世界や“グラス・オニオン”の構造ともリンクしています。デロルは、空虚な権威の象徴を視覚化した存在と言えるかもしれません。
燃え残った“問い”に、どう答えるか
本作を観終わったあと、爽快な気持ちと同時に、どこかモヤモヤした感覚が残りました。
マイルズは法的に裁かれないまま終わり、ヘレンは“破壊”という手段で真実を示す。「正義とは何か?」という問いを、ラストで観客に丸投げしているんですよね。
この作品が面白いのは、ただ犯人を暴いて終わるのではなく、「暴いたあと、どうする?」という問いを残してくるところ。ブランは真実を明らかにするけれど、行動はヘレンに委ねる。
そしてヘレンは、モナリザを燃やすという“禁忌”を犯してまで、マイルズの虚構を終わらせる。これは、「法では裁けない悪に対して、倫理を超えた行動が許されるのか?」という、かなり重いテーマです。
そしてもうひとつ、この映画が描いているのは、“見せかけの権力”と“本物の力”の違い。セレブたちは虚飾にまみれ、マイルズは空っぽの天才を演じている。でも、真実を見抜き、行動したのは、地味で素朴な小学校教師のヘレンでした。彼女こそが、物語の“核”となる存在だったと言えます。
本作は、ミステリーの皮をかぶった社会風刺と倫理の寓話。そしてラストに残るのは、「あなたならどうする?」という問い。モナリザを燃やす勇気があるか? 法を超えてでも真実を示すべきか? それとも、沈黙を選ぶか?
そんな問いを観客に託して、物語は静かに幕を閉じます。
オマージュ/カメオ出演
- 「そして誰もいなくなった」アガサ・クリスティ
孤島で殺人事件が起きるという設定は、クリスティの代表作への明確なオマージュ。 - 「名探偵ポワロ」シリーズ
ブノワ・ブランのキャラクター造形や推理スタイルは、ポワロを現代風にアレンジしたもの。 - 「007」シリーズ
「Among Us」をプレイするブランの姿や、バスローブ姿など、ダニエル・クレイグの“非ボンド”演出が逆オマージュ的。 - グラス・オニオン
ビートルズの楽曲名。歌詞には「Here’s another clue for you all / The walrus was Paul」という“謎解き”の要素もあり、映画の構造と重なります。 - 寄木細工の招待状
謎解きゲームの導入として、古典的なパズルボックスが登場。映画「CUBE」や「SAW」などの作品を連想させます。 - マーダー・ミステリー・パーティー
自分の殺人を推理させるという設定は、自己演出に満ちたセレブ文化への皮肉であり、同時に「スクリーム」などのメタホラー的構造にも通じます。 - Among Us(オンラインゲーム)
ブランが風呂場でゲームをするシーンは、パンデミック中の孤独と娯楽を象徴。 - スティーヴン・ソンドハイム
ブランのゲーム仲間として登場。「ウェストサイド物語」の作詞など、数多くのミュージカル作品を手がけた巨匠。 - アンジェラ・ランズベリー
ブランのゲーム仲間として登場。1984年から始まったテレビドラマ「ジェシカおばさんの事件簿」で主人公を演じました。 - ヨーヨー・マ
世界最高峰のチェリスト。バーディーのパーティーの参加者として登場(セレブ文化への皮肉)。 - セリーナ・ウィリアムズ
マイルズのジムのトレーナーとして登場。富裕層の“贅沢な孤島生活”を象徴。 - ジェレミー・レナーのホットソース
実在の俳優を架空の商品に仕立てたユーモア。小道具としても伏線回収に使われます。
Netflixの記事